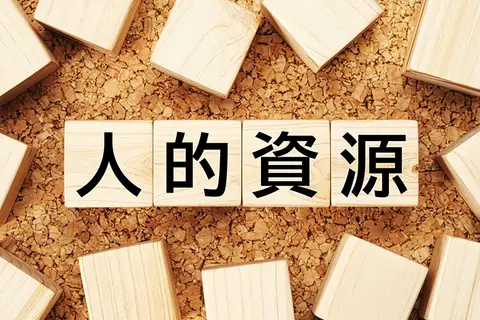企業の健康診断は義務?対象者や検査項目、実施のポイントを解説


従業員の健康診断の実施は、企業の義務です。企業は、従業員の健康と安全に配慮する責任を負っており、その一環として、定期的に健康診断を行うことが求められています。
しかし、対象者の範囲や検査項目など、どこまで対応するのか不明瞭な部分もあるのではないでしょうか。
ここでは、健康診断における企業の義務の範囲や、健康診断の種類のほか、健康診断費用を抑える方法など解説します。
健康診断の実施は企業の義務
定期的に健康診断を実施することは、労働安全衛生法第66条で定められた企業の義務です。
企業は、勤務時間や契約期間など一定の要件を満たす従業員に対し、適切な健康診断を実施しなくてはなりません。これに違反した場合は、労働安全衛生法第120条にもとづき、罰金が科せられる可能性があります。
なお、健康診断を実施するのは企業の義務ですが、従業員にも労働安全衛生法の定めによって健康診断を受ける義務があります。
健康診断を受けない従業員には、法律によって従業員に健康診断を受診する義務があることを説明しましょう。受けない理由をヒアリングし、健康診断を受けるメリットや必要性を伝えて、受診を促すことが大切です。
健康診断実施後の取り組み
健康診断は実施したら終わりではありません。労働安全衛生法では健康診断の実施に加えて、以下に紹介する健康診断実施後の取り組みについても企業の義務としています。
健康診断結果の通知
企業は、健康診断の結果を受診者全員に文書で通知する義務があります。異常がなかった人にも、きちんと文書で通知しましょう。ただし、本人が受診結果を病院から直接受領した場合には、企業から受診者に通知する必要はありません。
健康診断結果の保存と報告
企業は、健康診断結果について健康診断個人票を作成し、各健康診断によって定められた期間、保存する義務があります。
さらに常時労働者が50人以上いる事業所では、保存に加えて定期健康診断結果報告書を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。報告義務を怠った場合は、労働安全衛生法第120条にもとづき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
医師などからの意見聴取と保健指導の実施
企業は、医師などからの意見聴取や保健指導の実施義務も負っています。
健康診断の結果、異常所見が認められた従業員がいた場合、企業は健康保持のために必要な措置について産業医その他の医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなくてはなりません。
また、特に健康の保持に努める必要がある従業員については、医師や保健師による保健指導を行うよう努める必要があります。
健康診断の結果のみでは従業員の身体・精神状態を判断するのが難しい場合は、医師らによる面談を行います。
健康診断結果にもとづいた事後措置の実施
企業には、健康診断結果にもとづいた事後措置の実施義務もあります。
まずは健康診断の結果をもとに、従業員が問題なく業務に就くことができるか、医師による就労判定が行われます。
その後、企業は就労判定によって必要と判断した場合、当該従業員の労働時間の短縮や就業場所の変更などの措置を講じなければなりません。
健康診断の種類
事業者が実施する健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断に分けられます。
このほか、パソコンなどの情報機器を使用する情報機器作業(VDT作業)や騒音作業など特定の業務に関しては、視力や上肢の運動機能、聴力などそれぞれ特定の項目について厚生労働省から健康診断を実施するよう指針・通達などが出されています。
ここでは、一般健康診断と特殊健康診断について解説します。
一般健康診断:全職種の従業員に対して実施する健康診断のこと
一般健康診断は、すべての職種の従業員に対して実施する健康診断で、雇入れの際に行う健康診断や1年毎に行う定期健康診断など以下の5種類があります。5種類の違いは以下のとおりです。
■一般健康診断の種類
横にスライドしてください
|
種類 |
対象者 |
実施時期 |
労働基準監督署への報告 |
健康診断個人票の保存期間 |
|
雇入時の健康診断(安衛則第43条) |
常時使用する労働者 |
雇入れの際 |
必要なし |
5年 |
|
定期健康診断(安衛則第44条) |
常時使用する労働者 *特殊業務従事者を除く |
1年以内ごとに1回 |
常時使用する労働者が50人以上の場合は必要 |
5年 |
|
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者 |
左記業務への配置替えの際、および6ヵ月以内ごとに1回 |
5年 |
|
|
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) |
海外に6ヵ月以上派遣する労働者 |
海外に6ヵ月以上派遣する際、および帰国後、国内業務に就かせる際 |
必要なし |
5年 |
|
給食従業員の検便(安衛則第47条) |
事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 |
雇入れの際、および配置替えの際 |
必要なし |
5年 |
※1 多量の高熱物体を取り扱う業務、重量物の取り扱い等重激な業務、深夜業を含む業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務など
※安衛則とは労働安全衛生規則の略で、労働安全衛生法にもとづいて厚生労働省が制定した、労働の安全衛生などの基準を定めた省令のこと
※厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」(2016年3月)
一般健康診断の検査項目は、健康診断の種類によって異なります。
すべての企業に関係がある「雇入時の健康診断」および「定期健康診断」の項目を以下にご紹介します。
<一般健康診断(雇入時の健康診断・定期健康診断)の検査項目>
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 腹囲*、体重、身長*、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査等*
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量および赤血球数)*
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)*
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)*
- 血糖検査*
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査*
*印は、定期健康診断において、年齢などの要件を満たせば医師の判断で省略可能
特殊健康診断:有害業務に従事する従業員を対象に実施する健康診断のこと
特殊健康診断は、人体に有害な可能性がある業務に常時従事する従業員に対して実施する健康診断です。
有機溶剤健康診断や鉛健康診断など8種類のほか、じん肺健診や歯科医師による健診も特殊健康診断に含まれます。
それぞれの健康診断の違いは以下のとおりです。
■特殊健康診断の種類
横にスライドしてください
|
種類 |
対象者 |
実施時期 |
労働基準監督署への報告 |
健康診断個人票の保存期間 |
|
有機溶剤健康診断(有機則第29条) |
屋内作業場等における有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
5年 |
|
鉛健康診断(鉛則第53条) |
鉛取扱い業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
5年 |
|
四アルキル鉛健康診断(四鉛則第22条) |
四アルキル鉛取扱い業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
5年 |
|
特定化学物質健康診断(特化則第39条) |
特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および特化則別表第3(※1)に掲げる期間内ごと |
必要 |
5年(特別管理物質(※2)については30年) |
|
高気圧業務健康診断(高圧則第38条) |
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
5年 |
|
電離放射線健康診断(電離則第56条) |
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
30年 |
|
除染等電離放射線健康診断(除染電離則第20条) |
除染等業務に常時従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
30年 |
|
石綿健康診断(石綿則第40条) |
石綿等の取扱い業務に従事する労働者 |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
40年 |
|
じん肺健康診断(じん肺法第7条・第8条) |
新たに常時粉じん作業に従事する労働者 |
就業の際 |
必要(※4) |
7年 |
|
常時粉じん作業に従事している労働者 |
じん肺管理区分1(※3)は3年以内ごと、じん肺管理区分2および3は1年以内ごと |
|||
|
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に従事している労働者 |
じん肺管理区分2は3年以内ごと、じん肺管理区分3は1年以内ごと |
|||
|
歯科医師による健康診断(安衛則第48条) |
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、⻩りんその他⻭またはその |
雇入れの際、配置替えの際、および6ヵ月以内ごと |
必要 |
5年 |
※有機則:有機溶剤中毒予防規則、鉛則:鉛中毒予防規則、四鉛則:四アルキル鉛中毒予防規則、特化則:特定化学物質障害予防規則、高圧則:高気圧作業安全衛生規則、電離則:電離放射線障害防止規則、除染電離則:東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則、石綿則:石綿障害予防規則
※1 e-Govポータル「特定化学物質障害予防規則 別表第三(第三十九条関係)」
※2 ベンゼンやアスベストなど、労働安全衛生法にもとづき、特に注意して取り扱う必要がある有害な化学物質のこと
※3 じん肺健康診断の結果にもとづき、じん肺を区分したもの。詳しくは厚生労働省岐阜労働局「じん肺管理区分について」を参照
※4 毎年年末(12月31日時点)における実施状況について、翌年2月末日までに所轄労働基準監督署に報告書を提出
特殊健康診断の検査項目は、特定の有害な業務に従事する人の健康障害を予防したり、病気を早期発見したりすることが目的で、各種健康診断によって異なります。詳しい診断項目については、都道府県労働局または労働基準監督署へ問い合わせることで、確認できます。
例えば、高気圧業務健康診断の場合は、以下のとおりです。
<特殊健康診断(高気圧業務健康診断)の検査項目>
- 一次健康診断項目
- 既往歴および高気圧業務歴の調査
- 関節、腰もしくは下肢の痛み、⽿鳴りなどの⾃覚症状または他覚症状の有無の検査
- 四肢の運動機能の検査
- ⿎膜および聴⼒の検査
- ⾎圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 肺活量の測定
- 二次健康診断項目
- 作業条件調査
- 肺換気機能検査
- 心電図検査
- 関節部のエックス線直接撮影による検査
※厚生労働省静岡労働局「特殊健康診断の健康診断項目」
企業が健康診断実施義務を負う「労働者」の範囲
自社の従業員が、健康診断実施対象となる従業員(法律上の「労働者」)に当たるかどうかは、労働時間や労働条件によって判断します。
アルバイト・パート社員などは労働条件などで異なるため、企業は健康診断の実施対象者の条件を確認し、従業員が健康診断の実施対象者か、範囲を正確に把握する必要があります。
企業が健康診断の実施義務を負う「労働者」の範囲(健康診断の実施対象者)は以下のとおりです。
■健康診断の実施対象者
横にスライドしてください
|
雇用形態など |
実施対象の条件 |
実施対象か否か |
|
正社員 |
―― |
実施対象 |
|
アルバイト・パート社員 |
・契約期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれている、またはすでに1年以上の雇用実績がある |
実施対象 |
|
・契約期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれている、またはすでに1年以上の雇用実績がある |
義務ではないが実施が望ましい |
|
|
派遣社員・スタッフ |
―― |
対象外 |
|
従業員の家族や配偶者 |
―― |
対象外 |
|
役員 |
役員待遇であっても、工場長など労働者性の強い役職にある場合 |
実施対象 |
|
代表取締役など |
―― |
対象外 |
健康診断費用の相場と企業負担
健康診断は病気やケガの治療ではないので、自由診療扱いとなります。費用は医療機関によって異なりますが、一人あたり5,000円~1万5,000円程度が目安です。
これらの健康診断の実施費用は、法律上の定めはありませんが、健康診断を受診させる義務が企業にあることから、企業が負担するのが原則です。ただし、従業員が希望してオプションなど、基本項目以外の検査を受けた場合、その費用は従業員の負担にすることは問題ありません。
なお、健康診断の結果により再検査や精密検査が必要になった場合の検査費用や交通費は、健康診断には該当しないとされ、企業に負担義務はありません。しかし、企業が支払うことが推奨されています。
健康診断費用を抑える方法
健康診断の費用をできる限り抑えるには、以下のような方法が効果的です。自社に合う方法を検討し、実践してみましょう。
ヘルスケアアプリを活用する
ヘルスケアアプリの活用により、従業員の健康意識向上や健康活動への取り組みが進めば、再検査や精密検査が減り、企業と従業員全体としての健康診断費用を抑えられるでしょう。
ヘルスケアアプリには、食事や運動の記録による健康管理やアプリ内イベントを通じた健康活動の促進など、多彩な機能が備わっており、健康経営優良法人認定取得指標に準拠したアプリもあります。
健康経営優良法人認定制度については、以下の記事をご参照ください。
健康診断費用を福利厚生費にする
健康診断費用は、以下の条件をすべて満たせば、福利厚生費として全額を損金算入でき、健康診断費用を抑えることが可能です。損金算入とは、法人税の計算において、企業の収益から差し引ける費用のことです。
<健康診断費用を福利厚生費にする条件>
- 対象となる従業員全員が、健康診断を受けられる体制が整っている
- 健康診断の費用が常識の範囲内である
- 企業が医療機関に直接費用を支払っている
二次健康診断等給付を活用する
二次健康診断等給付を活用することで、健康診断費用を抑えることができます。
二次健康診断等給付とは、健康診断で異常が認められた場合に、二次健康診断および特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診できる労災保険の制度のことです。従業員にこの制度を利用してもらうことで、再検査費用の負担を軽減できます。
まとめ
- 企業は法律上の義務として、定期的に健康診断を実施しなければならない
- 健康診断実施後は、結果の通知、健康診断結果の保存や労働基準監督署への報告なども行う義務がある
- 正社員ほか、条件を満たすパート・アルバイト社員も健康診断の実施対象となる
- 健康診断費用は、基本的に企業負担となる。費用を抑えるには、ヘルスケアアプリの活用などが有効
従業員の健康管理についてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。
従業員の健康に配慮すべき理由、従業員の健康を促進する制度ご紹介しております。
※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。
※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。
健康経営優良法人認定基準に準拠した豊富なコンテンツを搭載するオールインワンアプリ
QOLism(キュオリズム)
歩数の自動計測や、写真でメニューを自動検出する食事記録、定期的なイベント開催等で、だれでも簡単に楽しく使い続けられる工夫が満載。
高い実効性で組合員さまや従業員さまの生活習慣改善をサポートします。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。