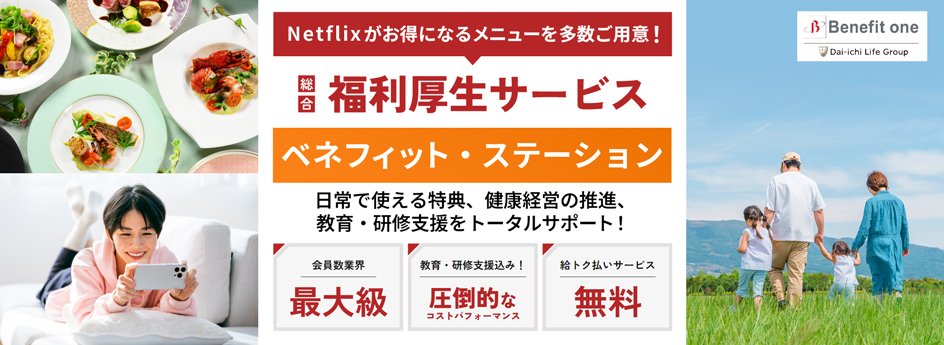インセンティブ制度とは?種類や事例、5つのメリットを解説


インセンティブ制度とは、従業員の意欲や行動に応じた報酬や評価を与えることでモチベーションを高め、企業の目標達成を後押しする制度です。給与や賞与とは異なり、従業員の働く姿勢などに応じて柔軟に与えられるため、近年の多様な働き方に対応した制度として注目されています。
一方で、インセンティブ制度には「モチベーションの向上以外にどんなメリットがあるのか?」「実際にどのような企業で、どのように制度が導入されているのか?」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
ここでは、インセンティブ制度の意味や、制度の導入によるメリット・デメリット、実際の企業事例、導入のステップなどを解説します。
インセンティブ制度とは?
インセンティブ制度とは、従業員の働く姿勢、行動や成果に応じて報酬や評価を与えることで、企業の目標達成を後押しする仕組みです。そもそも「インセンティブ(Incentive)」とは、英語で「刺激」「動機づけ」を意味する言葉で、ビジネスにおいては人を行動に駆り立てる報酬や仕組みを指します。
そのためインセンティブの種類には、金銭的な報酬だけでなく、承認・称賛・成長支援など、非金銭的な要素も含まれます。
■インセンティブの主な種類
|
分類 |
主な内容 |
|
金銭的インセンティブ |
・業績連動型賞与:目標達成度に応じて賞与を支給する ・インセンティブ給:個人の成果や特定の行動に応じて、基本給とは別に金銭を支給する ・特別手当、一時金:プロジェクト達成や貢献度に応じて、スポット的な報奨金を支給する ・ポイント付与:物品やサービスと交換可能なポイントを付与する |
|
非金銭的インセンティブ |
・表彰制度:功績・貢献を公に認め、モチベーションを高める ・キャリア機会の提供:昇進・昇格などの成長チャンスを与える ・自己成長支援:研修・資格取得支援など学びの機会を提供する |
非金銭的な要素には、広くはフレックス制度やリモートワークの導入といった福利厚生の充実も該当します。そのため、インセンティブ制度は単なる給与制度とは異なり、従業員が自分から仕事に対して前向きに行動できるようにするための、動機づけも含めた施策といえるでしょう。
インセンティブ制度が注目される背景
かつて日本の多くの企業では、「終身雇用」と「年功序列」に代表される、在籍年数や年齢に応じて処遇が決まる人事制度が主流でした。しかしバブル崩壊後、こうした制度では企業の競争力維持が難しくなったため、成果や能力にもとづいて報酬を決定する「成果主義」が広がっていきました。
ところが、成果主義は行き過ぎると、過度な競争や短期的な結果偏重を招いてしまいます。こうした反省を踏まえ、近年、注目されている評価の仕組みがインセンティブ制度です。
インセンティブ制度は、成果のほか、従業員の意欲や行動を評価するため、従業員の成長を促す柔軟な制度といわれています。多様な働き方が広がり、従来の画一的な評価制度では対応しきれない現代において、従業員の意欲や自主性を引き出す仕組みとして、インセンティブ制度の必要性が高まっているのです。
インセンティブ制度の目的
インセンティブ制度を導入する目的は、単なる報酬の強化ではなく、従業員の望ましい行動を引き出し、企業戦略や組織課題の解決につなげることです。企業は制度を通じて「従業員の何を評価し、どう報いるか」を明確にし、自社に合った組織文化の形成を図る必要があります。
インセンティブ制度の導入によるメリット
インセンティブ制度は、従業員だけではなく、企業全体の成長や組織活性化にも影響を与える重要な仕組みです。ここでは、インセンティブ制度の導入によって得られる代表的なメリットを5つ紹介します。
従業員のモチベーションを高める
インセンティブ制度の最大のメリットは、従業員のモチベーション向上です。仕事に対する成果や行動に対して、インセンティブが与えられることで、従業員は自分の努力が正当に評価されていると実感でき、日々の業務への意欲が高まります。
行動の質と目標達成への意識が高まる
インセンティブ制度により「自社のためにどのような行動が望ましいか」という評価基準が明確になることで、従業員の行動の質と目標達成への意識が高まる点もメリットです。これにより、従業員が目標達成に向けて自発的に行動するようになり、短期的な成果だけでなく、中長期的な成長にもつながるでしょう。
営業職のように売上数字で評価しやすい職種だけでなく、人事・経理・総務といったミドルバック職種においても、インセンティブ制度は有効です。以下のように、各部門の特性に応じた具体的な評価指標を設定することができます。
<ミドルバック職のインセンティブの例>
- 人事部門
「従業員エンゲージメントスコアを前年比10%向上させた」という成果に対してインセンティブを付与 - 経理部門
「経費精算システムの導入により処理時間を50%短縮した」という業務効率化の貢献に対してインセンティブを付与 - 総務部門
「社内問い合わせに対する24時間以内の回答率を95%以上達成した」という顧客サービス向上に対してインセンティブを付与
企業理念やビジョンへの理解が深まる
インセンティブ制度では、企業の理念やビジョンに沿った行動を評価基準に組み込むことが可能です。これにより、従業員が理念やビジョンを意識しながら日々の業務に取り組むようになり、理解がより深まるというメリットがあります。さらに、理念やビジョンの共有を通じてチーム全体の一体感が高まることで、組織の方向性をより明確に感じられるようになるでしょう。
従業員の定着率向上と採用力が強化される
魅力的なインセンティブ制度が整備されている企業は、従業員の満足度が高まり、離職率の低下につながります。さらに、この制度の内容を採用広報などで積極的に発信することで、求職者にとっての企業の魅力のひとつとなり、採用力の強化につながる点もメリットといえるでしょう。
人件費の最適化が図れる
固定的な支給ではなく、成果や貢献に応じた柔軟な報酬設定をすることで、人件費の最適化を実現できる点もメリットです。経営状況や組織の方針にあわせて柔軟に見直すことができます。
インセンティブ制度の導入によるデメリット
組織にとって、インセンティブ制度には多くの利点がありますが、設計や運用を誤ると、逆効果にもなりかねません。ここでは、制度導入にあたって注意すべき主なデメリットを3つ紹介します。
過度な競争が協力体制を損なうおそれがある
インセンティブ制度の内容によっては、従業員同士が成果を競い合う構図が強まりすぎてしまう点がデメリットです。こうした過度な競争は、職場の連携やチームワークを弱める要因となり、制度本来の目的から逸れてしまう可能性があるため注意が必要です。
不公平感が従業員の不満につながりかねない
インセンティブの評価基準や支給条件が不明確であったり、特定の業務や職種に偏っていたりすると、「自分の努力が正当に評価されていない」といった不公平感が生まれやすくなります。このようなデメリットは、従業員の不満や離職にもつながりかねません。
制度の理解不足により形骸化する
インセンティブ制度が複雑になりすぎると、従業員にうまく理解されず、期待した効果を発揮できないことがあります。制度の目的や運用ルールが浸透しなければ、形だけの制度となり、モチベーション向上どころか逆に混乱を招きかねない点もデメリットといえます。
インセンティブ制度の導入事例
インセンティブ制度を導入して成功した企業には、もともとどのような課題があったのでしょうか。ここでは、総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」が提供する「インセンティブ・ポイント」の導入事例を紹介します。
株式会社ソラスト:離職率改善とサービス向上を実現した「ソラストポイント」
課題
医療、介護、保育の3事業を展開する株式会社ソラストでは、人手不足や業務負担の集中が課題となっており、離職率は一時40%近くに達していました。「がんばっても評価されにくい」「感謝される機会が少ない」といった声も多く、従業員のモチベーション低下が顕在化していました。
導入したインセンティブ制度
- 「ソラストポイント」と名付けられたインセンティブ・ポイントプログラムを導入
- 園長に毎月ポイントを付与し、現場の貢献に応じてスタッフに配分
- ポイントとあわせて「ありがとう」などのメッセージを添え、みんなの前で表彰
- 掃除や行事の準備など、目立たない日常の行動も評価対象に
- 獲得したポイントは自由に商品と交換可能(ベネフィット・ステーションのカタログ利用)
- 制度は保育事業から始まり、現在は全社(約25,000名)に展開中
制度導入後の効果
従業員間の承認文化が育まれ、離職率は2年連続で10%未満に改善。従業員満足度とともに、保護者からの評価も年々向上し、サービス品質の底上げにもつながりました。
損保ジャパンパートナーズ株式会社:営業稼働率2倍を実現した「SHSポイント交換プログラム」
課題
保険商品を扱う損害保険ジャパンのグループ企業として、全国100拠点以上の営業体制を有する損保ジャパンパートナーズ株式会社では、営業組織全体の底上げが課題でした。
従来の表彰制度「SHSアワード」は一部の業務トップ層のみが対象となっており、営業以外のサポート職やパート従業員の努力が可視化されにくい状況が続いていました。
導入したインセンティブ制度
- インセンティブ・ポイントプログラムとして「SHSポイント交換プログラム」を導入
- 営業職に限らず、サポート職やパート職も含めた幅広い職種にポイントを付与
- 社内キャンペーンと連動し、目標達成への取り組みに応じてポイントを配布
- 獲得したポイントは自由に商品と交換可能(ベネフィット・ステーションのカタログ利用)
- 表彰制度を「記念品支給」から「ポイント交換型」に変更し、実用性と自由度を向上
制度導入後の効果
制度導入後は、営業稼働率が前年の約2倍に向上し、年間業績目標も達成。対象者の拡大により、表彰の機会が広がり、職場全体の士気が向上しました。
また、獲得したポイントを通じて従業員自身やその家族にも還元される仕組みにより、働きがいの実感にもつながっています。
▼「インセンティブ・ポイント」については、以下のページをご参照ください。
インセンティブ制度の導入ステップ
インセンティブ制度を効果的に運用するには、事前の準備や制度設計など、しっかりとした導入手順を踏む必要があります。ここでは、インセンティブ制度を導入するための基本的なステップを解説します。
STEP1:目的を明確化する
インセンティブ制度の導入を検討する最初のステップは、制度の目的を明確にすることです。目的によって、導入すべきインセンティブの種類や評価方法が変わるため、必ず行いましょう。
STEP2:制度設計をする
インセンティブ制度を導入する目的が明確になったら、次に具体的な制度設計を行います。インセンティブの種類や評価基準、報酬の決定方法、提供タイミングなど、運用ルールを詳細に定めます。
STEP3:制度の導入後は評価・改善をする
インセンティブ制度を導入したら、その効果を定期的に評価します。期待した成果が得られていない場合は、制度の改善が必要です。柔軟に見直しを重ねることが、制度を定着・成功させるポイントとなります。
まとめ
- インセンティブ制度とは、従業員の成果や行動に応じて報酬や評価を与え、従業員のモチベーション向上と企業の目標達成を後押しする仕組み。
- インセンティブには、賞与やポイントなどの金銭的インセンティブと表彰、成長支援などの非金銭的インセンティブがある。
- インセンティブ制度の設計によっては、従業員のモチベーション向上、行動の質の改善、企業理念の浸透、定着率や採用力の向上、人件費の最適化など多様なメリットが期待できる。
- インセンティブ制度の設計を誤ると、過度な競争や不公平感、制度の形骸化といったデメリットが生じやすい
- インセンティブ制度導入のステップは、「目的の明確化」「制度設計」「導入後の評価・改善」の3段階が基本。
第一生命がご紹介する福利厚生サービス【ベネフィット・ステーション】
第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが提供するサービス概要資料を無料で提供いたします。
※「ベネフィット・ステーション」は株式会社ベネフィット・ワンの登録商標です。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。