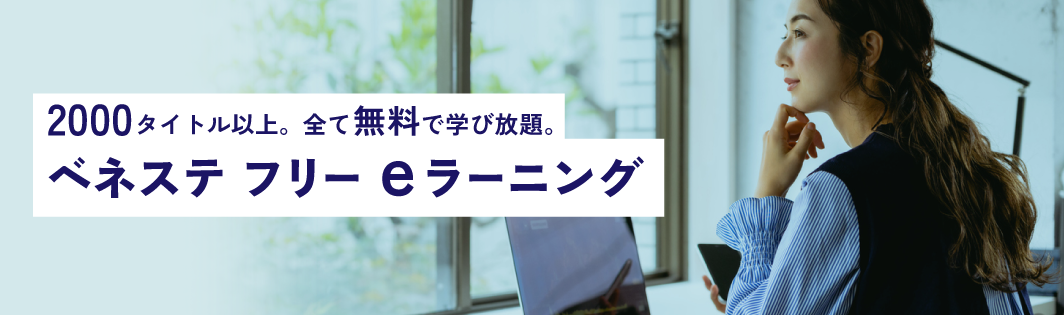ハラスメント研修の内容とは?実施する目的や講習内容を解説


近年、職場でのハラスメント問題が社会的に注目され、企業にはより厳格な対応が求められるようになりました。実際に、「パワハラやセクハラをしてしまわないか不安」といった声も職場で聞かれるようになり、ハラスメント研修の必要性が高まっています。
職場でのハラスメントは、被害者はもちろん、組織全体に大きな影響を与えかねない深刻な問題ですが、適切な知識と対策があれば防ぐことが可能です。
ここでは、ハラスメントの定義と種類、ハラスメント研修の具体的な内容のほか、研修実施後のフォローアップについても詳しく解説します。
ハラスメントとは?
ハラスメント(harassment)とは、「嫌がらせ」「いじめ」を指す言葉で、相手の人格や尊厳を傷つける行為全般を意味します。ハラスメントかどうかの判断において大切なのは、行為者の意図ではなく、受け手がどう感じるかという点です。
受け手の尊厳が傷ついた場合は、たとえ行為者に悪意がなくてもハラスメントに該当する可能性があります。
近年、職場でのハラスメント問題が深刻化し、労働者の精神的健康や企業の生産性に大きな影響を与えていることから、国はハラスメント対策の強化に乗り出しました。その結果、2020年の労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント(パワハラ)の防止措置が義務化され、2022年4月からは中小企業も対象となっています。
企業にとって、パワハラだけではなく、セクシュアルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)など、種類を問わずハラスメント対策が必要です。
こうした背景から、従業員一人ひとりがハラスメントについて正しい知識を身につけ、適切な行動を取れるようにするためのハラスメント研修の重要性が高まっています。
ハラスメントの種類
職場で発生するハラスメントには、主に以下の種類があります。
これらのハラスメントは、職場環境を悪化させ、従業員の心身の健康に深刻な影響を与えるため、適切な対策が不可欠です。
<主なハラスメントの種類>
- パワーハラスメント(パワハラ):職場の優位性を背景とした言動
- セクシュアルハラスメント(セクハラ):性的な言動による嫌がらせ
- マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠・出産・育児休業等に関する嫌がらせ
- ケアハラスメント(ケアハラ):介護との両立を困難にする嫌がらせ
- SOGIハラスメント(ソジハラ):性的指向・性自認に関する嫌がらせ
▼ハラスメントの事例については、以下の記事をご参照ください。
ハラスメントが起きてしまう原因
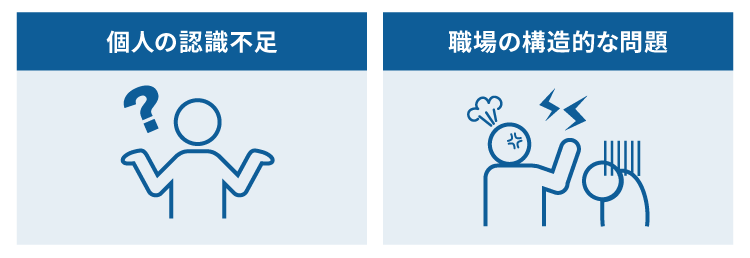
ハラスメントが発生する原因は、大きく「個人の認識不足」と「職場の構造的な問題」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの要因について詳しく解説します。
個人の認識不足
ハラスメントを起こす本人が、この問題に対して正しい知識を持っておらず、無意識に加害者になってしまうケースが見られます。
特に以下のような状況で発生しがちです。
<認識不足で起こりやすいハラスメント>
- 「指導のつもり」が相手に威圧感を与えている
- 世代間の価値観の違いを理解していない
- 相手の立場や状況への配慮が不足している
- 「これくらいは大丈夫」という思い込みがある
- 部下とのコミュニケーション不足から誤解が生じる
また、ハラスメントに対する認識が十分でないと、部下を指導する際に「この言い方はハラスメントと受け取られるのではないか」と過度に心配し、効果的な指導ができなくなるという逆の問題も起こります。
職場の構造的な問題
職場の雰囲気や環境がハラスメントを起こりやすくしている場合があります。具体的には、以下のような職場でハラスメントが発生しやすくなっています。
<ハラスメントが起きやすい職場環境の例>
- ミスが許されないような過度なストレスがかかる
- 職場の責任者の権限が強すぎる
- 上司に意見や提案を言いにくい雰囲気がある
- 長時間労働が常態化し、心理的余裕がない
- ハラスメントに対する組織の方針が明確でない
- 相談窓口がない、または機能していない
- 正規・非正規・外国籍など、さまざまな立場の人が一緒に働いている
このような環境では、個人の意識が高くてもハラスメントが発生しやすくなるため、職場全体の問題として対策を講じる必要があります。
ハラスメント研修を実施する狙い
ハラスメント研修の実施そのものは法律で明記された義務ではありません。
しかし、企業には労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)によりハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられており、結果的にハラスメント研修の実施が不可欠となっています。
また、ハラスメント研修の実施には、より良い職場環境を構築するという重要な目的もあります。
労働施策総合推進法で事業主に対して求める主な措置は下記のとおりです。
<企業に求められる主な措置>
- 事業主の方針の明確化および、その周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメント発生後の迅速かつ適切な対応
- 当事者のプライバシー保護、不利益取り扱いの禁止
など
※参考:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第九章
企業に求められる主な措置の中でハラスメント研修は、1つ目の「周知・啓発」において重要な役割を果たします。
研修を通じて従業員にハラスメントに関する正しい知識を伝え、防止への意識を高めることで「ハラスメントを起こさない組織づくり」を実現することが狙いです。
具体的には、予防方法の習得と発生時の適切な対応方法を学ぶことで、ハラスメントのない働きやすい職場環境の構築を目指します。また、管理職には部下への適切な指導方法を身につけてもらい、一般職には自分自身がハラスメントの被害者にも加害者にもならないための知識を提供します。
ハラスメント研修の内容
ハラスメント研修では、参加者がハラスメントについて正しく理解し、実践的な対応方法を身につけられるよう、体系的なカリキュラムを組むことがポイントです。
ここでは、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会の研修内容を例として、具体的な研修項目をご紹介します。
<研修の基本情報>
- 参加想定人数:6~24名
- 研修対象:一般社員、管理監督者
- 形式:ミニ講義および演習・グループワーク
- 所要時間:180~360分(休憩時間を含む)
■ハラスメント研修内容(例)
横にスライドしてください
|
研修項目 |
具体的な内容 |
所要時間 |
|
ハラスメントとは |
・パワーハラスメントの定義 |
10~20分 |
|
パワーハラスメントの現状 |
・パワーハラスメントの起きやすい組織風土とは |
50~100分 |
|
パワーハラスメントの背景 |
・職場環境の悪化と雇用不安の助長 |
10~20分 |
|
セクシュアルハラスメントの現状 |
・セクシュアルハラスメントの認識度は |
30~60分 |
|
ハラスメントの影響 |
・職場、被害者、行為者への影響 |
30~60分 |
|
企業が配慮すべき3つの対策と実務 |
・一般防止策 |
|
|
相談対応ふりかえり |
・事例検討とロールプレイ |
50~100分 |
※出典:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会「ハラスメント研修」
このハラスメント研修の特徴は、実際の事例を用いたケーススタディで理解を深め、ロールプレイングを通じて実践的なスキルを習得できることです。さらに、管理監督者と一般社員それぞれの立場に応じた内容で研修を行い、グループワークによる意見交換と気づきを促す内容となっています。
あくまで、これは一例です。ハラスメント研修は参加者の階層や職場の課題に応じてカスタマイズし、より効果的な学習効果を目指しましょう。
ハラスメント研修実施後のフォローアップ
ハラスメント研修は実施して終わりではありません。研修の効果を最大化し、持続的な職場環境の改善を図るためには、実施後のフォローアップが重要です。
ここでは、効果的なフォローアップの方法について解説します。
面談やアンケートなどのフォローアップを実施する
ハラスメント研修実施後は、参加者の理解度や意識の変化を把握するため、以下のようなフォローアップを行いましょう。
<ハラスメント研修後の主なフォロー内容>
- 研修直後のアンケート調査による理解度の確認
- 研修から一定期間後(1ヵ月後、3ヵ月後など)の追跡アンケート
- 管理職との個別面談による職場での実践状況の確認
- 職場環境の変化に関する全社的な調査
- 相談窓口への相談件数や内容の分析
これらのフォローアップにより、研修の効果を測定し、職場におけるハラスメント防止の取り組み状況を継続的にモニタリングできます。
定期的に研修内容をアップデートする
ハラスメントに関する法律や社会情勢は変化するため、研修内容も定期的に見直し、アップデートすることが必要です。
<ハラスメント研修でアップデートする内容の例>
- 法改正や新しいガイドラインへの対応
- 社会情勢の変化に応じた事例の更新
- 職場で発生した問題を踏まえた内容の改善
- 参加者からのフィードバックを反映した改良
- 新しいハラスメントの類型への対応
また、入社時や昇進時など、定期的な研修機会を設けることで、組織全体のハラスメント防止意識を維持・向上させることができます。
なお、ベネフィット・ステーションが提供している「ベネステ フリーeラーニング」では、ハラスメント防止に関するeラーニング講座もあり、企業の研修ニーズに応じたコンテンツが利用可能です。
▼ベネフィット・ステーションのネットラーニング講座についてはこちらをご参照ください
まとめ
- ハラスメントとは「嫌がらせ」「いじめ」を指す言葉で、受け手の尊厳が傷ついた場合はハラスメントに該当する
- ハラスメントが起こる原因には大きく「個人の認識不足」「職場の構造的な問題」の2つがある
- ハラスメント研修の目的は「ハラスメントを起こさない組織づくり」であり、予防方法と発生時の対応方法を学ぶことで働きやすい職場環境を構築する
- 研修内容は基礎知識から実例検討、ロールプレイングまで体系的に構成され、参加者の階層に応じてカスタマイズする
- 研修実施後は面談やアンケートによるフォローアップを行い、定期的な内容のアップデートが効果的である

- 現職:
- 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 中部支部 社会貢献事業部 プロジェクトリーダー
- ウエルネスアットワーク株式会社 代表取締役
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 静岡産業保健総合支援センター 相談員・促進員